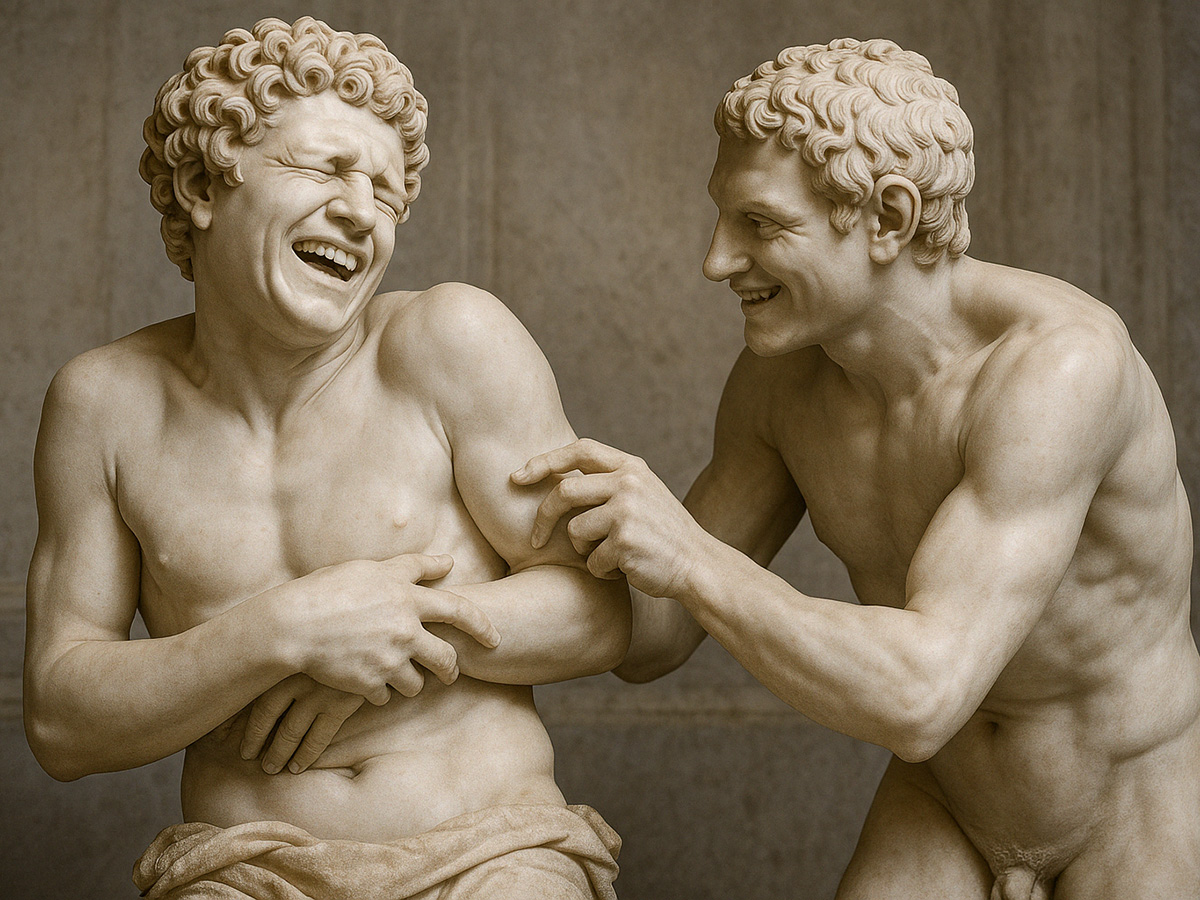
- なぜ自閉症の人は自己刺激行動(スティミング)をやめられない、もしくはやめてはいけないのですか?
- 自閉症の人が他人から触れられた時と自分で自分に触れた時で、感覚や脳の反応はどのように違うのですか?
- センサー過敏や鈍感さはどのような脳の仕組みによって起こるのですか?
自分で自分の体に触れたときと、他人から触れられたときでは、私たちの脳の反応は明らかに異なります。
たとえば、自分で自分をくすぐってもあまりくすぐったくないのに、他人にくすぐられると強い感覚を感じることは多くの人が経験しているでしょう。
これは、私たちの脳が「自分が動かしている」という予測を立て、刺激に対する反応を事前に弱めているからだとされています。
こうした脳の仕組みは、自閉症スペクトラム(ASD)を持つ人々においてはどうなのでしょうか。
アメリカのロチェスター大学のエミリー・アイゼンシュタイン博士らの研究チームは、この疑問に答えるために、最先端のバーチャルリアリティ(VR)技術と脳波測定(EEG)を組み合わせた興味深い実験を行いました。
自閉症スペクトラムの特徴として知られる感覚の過敏性や鈍感さ、とくに触覚に関しては、日常生活で大きな影響を与えることがあります。
特定の服の素材を不快に感じたり、軽いタッチを非常に強い刺激として感じたりする人もいます。
また、自分自身で身体を触るような行動、いわゆる「セルフスティミング」(自己刺激行動)も、自閉症の人々によく見られる行動の一つです。
この行動は、不快な刺激を避けたり、心地よい感覚を得たりするために行われると考えられていますが、その正確な脳の仕組みについては、これまであまり知られていませんでした。

研究チームは、30人の自閉症スペクトラムを持つ成人と30人の一般的な発達を遂げた成人(定型発達)を対象に実験を行いました。
参加者は、それぞれがVRヘッドセットを装着し、自分の指先に装着した小さな装置から振動刺激を受けます。
実験では、自分自身が指を動かしてVR空間内の仮想の指に触れた時(自己発生=アクティブ条件)と、VR空間内で仮想の指が自動的に動いて参加者の指に触れた時(外部発生=パッシブ条件)の両方の状況で脳波が記録されました。
また、刺激には規則的な短い振動(標準刺激)と、突然少し長くなる不規則な振動(逸脱刺激)の2種類があり、参加者にはこの違いについて事前に知らされていません。
こうして得られた脳波のデータから、とくに注目したのは3つの反応でした。
一つ目は「N1」と呼ばれる反応で、刺激が与えられた約100ミリ秒後に現れ、刺激が届いたことを脳が認識したことを示します。
二つ目は「MMN(ミスマッチ陰性電位)」と呼ばれる反応で、これは刺激が予測していたパターンと異なった時に現れ、約200ミリ秒後に観察されます。
そして三つ目は「P300」という反応で、刺激に対して注意を向けたり、驚きを感じたりした時に約300ミリ秒後に現れます。
これらの脳波の反応を見ることで、刺激に対して脳がどのように処理を行っているかを詳細に調べました。
結果はとても興味深いものでした。
まず、自閉症の人は、外部から与えられた刺激に対する最初の脳波反応(N1)が定型発達の人より小さいことが分かりました。
これは、自閉症の人が他人から触れられた刺激に対して、脳の初期段階で少し鈍感である可能性を示唆しています。
一方、自分自身が起こした刺激に対する脳波反応は、定型発達の人とほぼ同じでした。
このことから、自閉症の人は自分自身による刺激には普通に反応するものの、「他人が与えた刺激」と「自分が与えた刺激」の違いを脳内で十分に区別していないことが考えられます。
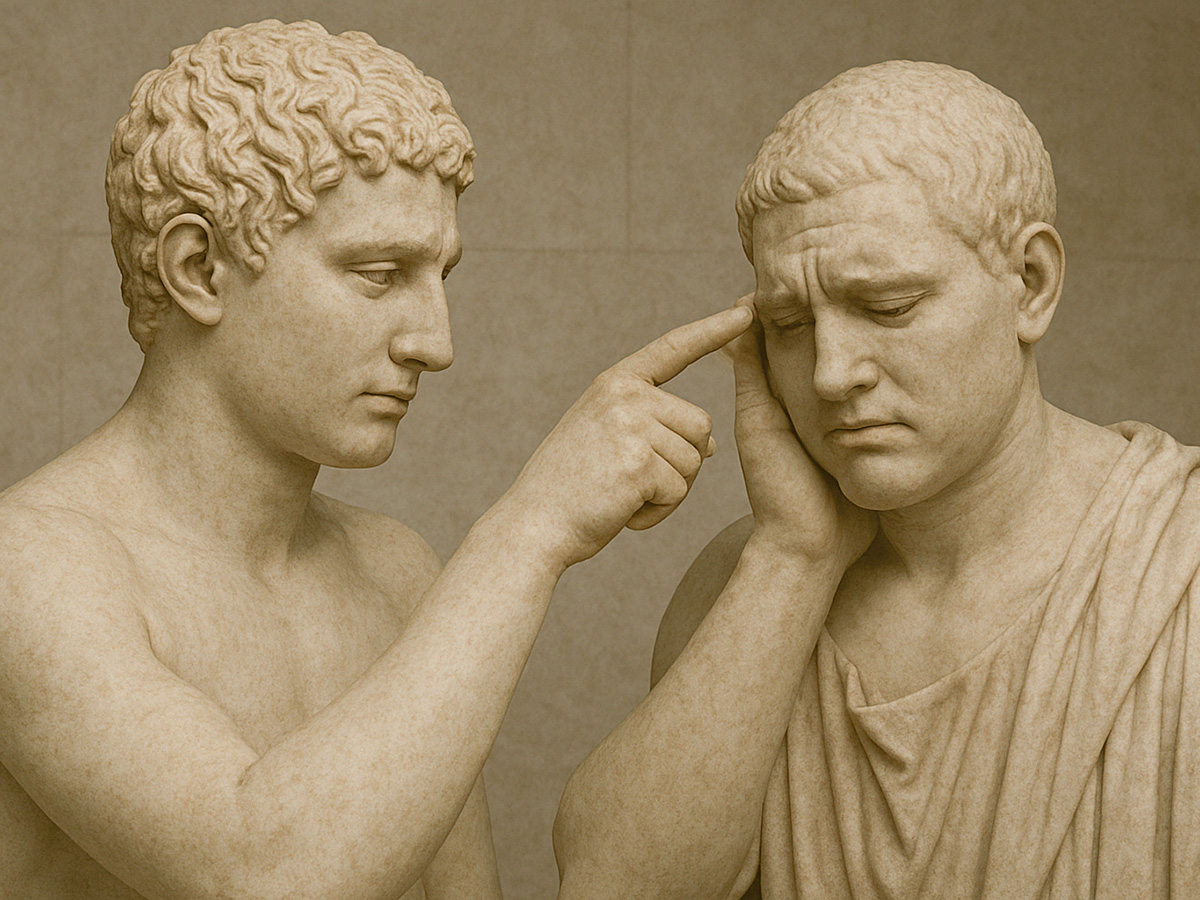
次に、刺激のパターンが突然変化したときの脳の反応(MMN)については、自閉症の人と定型発達の人の間に差はありませんでした。
この結果は、自閉症の人も外部環境の中で起こるパターンの変化や異常に対して正常に気づいていることを意味しています。
さらに、自閉症の人は、刺激に対する注意や驚きを示すP300の反応が全体的に大きいことが明らかになりました。
これは、自閉症の人が刺激を脳内で強く処理し、一般の人よりも強い反応を示している可能性を示しています。
この結果から、自閉症の人は刺激に対して単に鈍感なわけではなく、むしろ強く反応しているものの、その反応の仕方やタイミングが一般の人と異なっている可能性があることが分かりました。

この研究の意義は大きく、なぜ自閉症の人が特定の刺激を避けたり、自己刺激行動を行ったりするのかについて、新しい理解を与えるものです。
刺激が自分自身で起こしたものであるか、他者が与えたものであるかという区別が曖昧になると、感覚処理が複雑になり、環境に適応することが難しくなることも考えられます。
また、この脳の反応パターンを理解することにより、より適切な環境の整備や感覚刺激の管理方法を考える手がかりになるでしょう。
今後の研究では、なぜこのような脳の反応が起こるのか、そのメカニズムをさらに詳細に解明することが期待されています。
また、こうした科学的知見が、教育や療育の場面で具体的にどのように活用されるのかについても、今後注目していきたいところです。
(出典:NeuroImage)(画像:たーとるうぃず)
「刺激が自分自身で起こしたものであるか、他者が与えたものであるかという区別が曖昧」
だからこそ、楽しいのかもしれませんね。
うちの子もずっと自己刺激行動(スティミング)はしています。
体を傷つけてしまうほどでなければ、そのままほうっておいてほしいと私は思います。
機嫌がわかったりする、感情表現ともなっているので。
(チャーリー)



























