
- なぜ最近、ADHDやASDの診断を受ける大人が増えているのか?
- 薬に頼らずにADHDやASDの問題に向き合う有効な方法は何か?
- 社会での多様性の受け入れは、個々の特性や個性をどう尊重することにつながるのか?
近年、「大人の発達障害」という言葉を耳にする機会が急激に増えています。
中でも、「ADHD(注意欠陥・多動性障害)」や「ASD(自閉スペクトラム症)」と診断される成人の数が世界的に急増し、大きな話題となっています。一体なぜ、このような現象が起きているのでしょうか。
ドイツの研究者で、経済学・国際法・心理学の博士号を持つベンジャミン・コッホは、2025年に発表した研究で、成人のADHDやASDの診断数が増え続ける背景を詳しく調査しました。
その結果、診断基準の変化や社会的な影響が、この「診断の増加」に大きく関係していることが明らかになりました。
実は、ADHDやASDは昔からある概念ですが、もともとは子ども特有の障害だと考えられていました。
1968年の診断基準(DSM-II)では、「子ども時代に見られる過度な多動性」だけが診断対象でした。
その後、精神医学の診断基準が改訂されるたびに、その基準は徐々に緩和されました。
とくに2013年のDSM-5では、「症状の始まりの年齢」が12歳までに引き上げられたり、「症状の数」が減らされたりして、成人の診断が容易になりました。
これにより、それまでは診断されなかった大人が次々とADHDやASDと診断されるようになったのです。
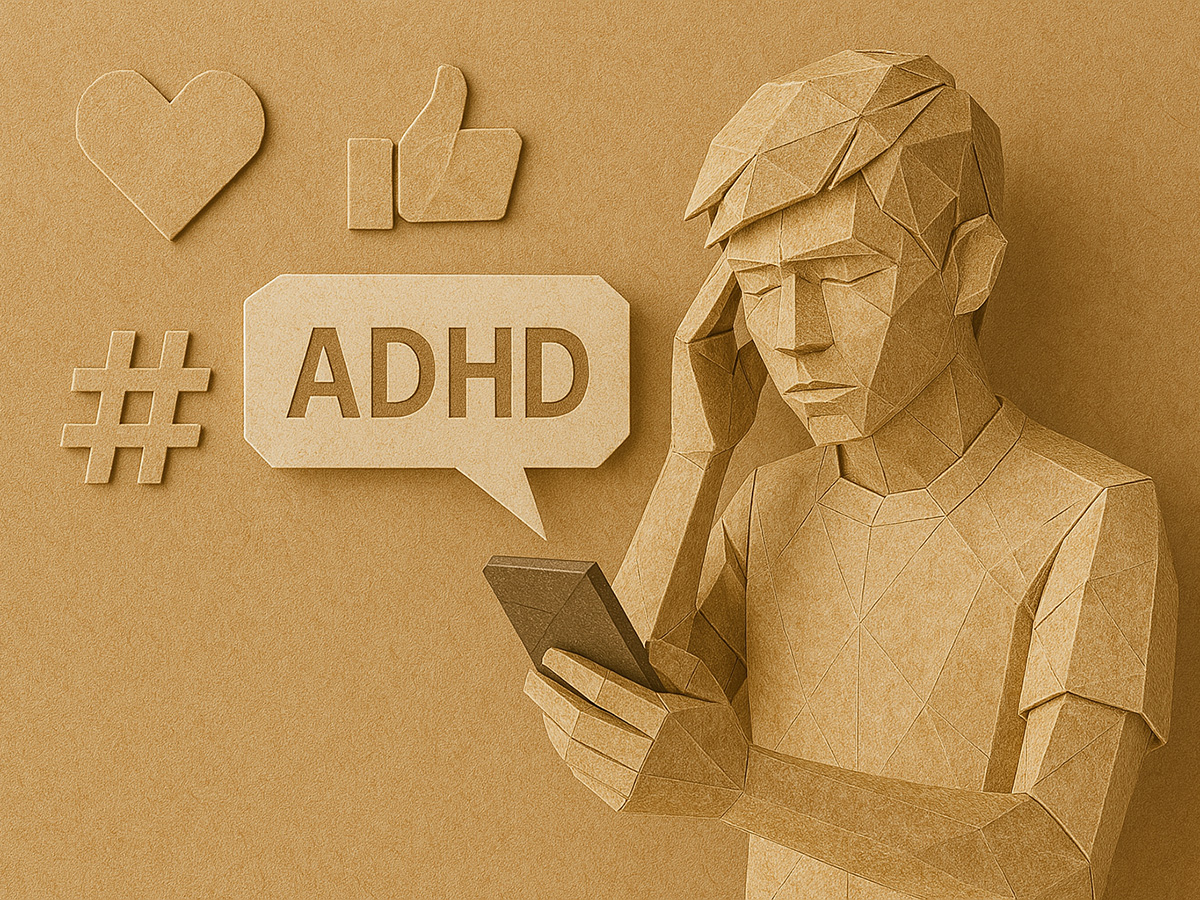 診断数の増加には、SNSやインターネットの影響も大きいとコッホ博士は指摘します。
診断数の増加には、SNSやインターネットの影響も大きいとコッホ博士は指摘します。
「あなたもADHDかも?」
というチェックリストがネット上に広まり、多くの人が自己診断を始めました。
とくに若い世代では、SNS上で発達障害についての情報が広がり、自分の特徴がこれに当てはまるのではないかと考える人が増えました。
これは一見、障害への理解や啓発が進んだように見えますが、その一方で、正常な個人差までもが病気として扱われる危険性も指摘されています。
実際にADHDやASDの診断を受けることにはメリットもあります。
それによって、これまで「怠け者」「注意力がない」と批判されてきた人が、「これは自分のせいではない」と感じられるようになります。
薬物療法によって、注意力が改善したり、生活がしやすくなったりするケースも確かに存在します。
しかし一方で、診断を受けた多くの成人が、薬(メチルフェニデートなど)を服用するようになった結果、薬への依存や副作用の問題も生じています。
また、薬は症状を一時的に抑えることはできますが、根本的な問題を解決するわけではありません。
薬物療法が長期的な解決策になり得ないという限界も、研究で明らかになっています。
では、薬に頼らず、持続可能で副作用のない方法でADHDやASDの問題に向き合うことは可能なのでしょうか。
ここで注目されているのが「マインドフルネス」という心理的アプローチです。
マインドフルネスとは、「今この瞬間」に注意を集中し、自分の感情や考えを否定せずに受け入れる心のトレーニングです。
たとえば、マインドフルネス瞑想などを通じて、自分が感じていることをありのままに観察し、感情に振り回されないようにするスキルを身につけます。
 研究では、このマインドフルネスがADHDやASDの成人に非常に有効であることが分かっています。
研究では、このマインドフルネスがADHDやASDの成人に非常に有効であることが分かっています。
マインドフルネスを実践した人たちは、注意力が向上し、感情のコントロールがうまくなり、衝動性や不安、ストレスが大幅に軽減されました。
とくに「マインドフルネス認知療法(MBCT)」や「マインドフルネスストレス低減法(MBSR)」というプログラムは、注意力や感情の管理能力を高める効果があることが、実証研究で明らかになっています。
さらに重要なのは、マインドフルネスが症状を「消す」のではなく、症状とうまく付き合う方法を教えてくれる点です。
ADHDやASDの特性を病気や障害ではなく、個性の一部として理解し、尊重することができるようになります。
実際に、この方法を試した人たちからは、「自分の弱点だと思っていたものが、強みや個性として活かせるようになった」という声も多く寄せられています。
コッホ博士は、これからの社会が、ADHDやASDなどを障害のように考えるのではなく、多様な個性を受け入れ、尊重する方向に変わる必要があると強調しています。
診断基準の見直しや、薬に依存しないマインドフルネスなどの心理的サポートの普及が、今後ますます重要になるでしょう。
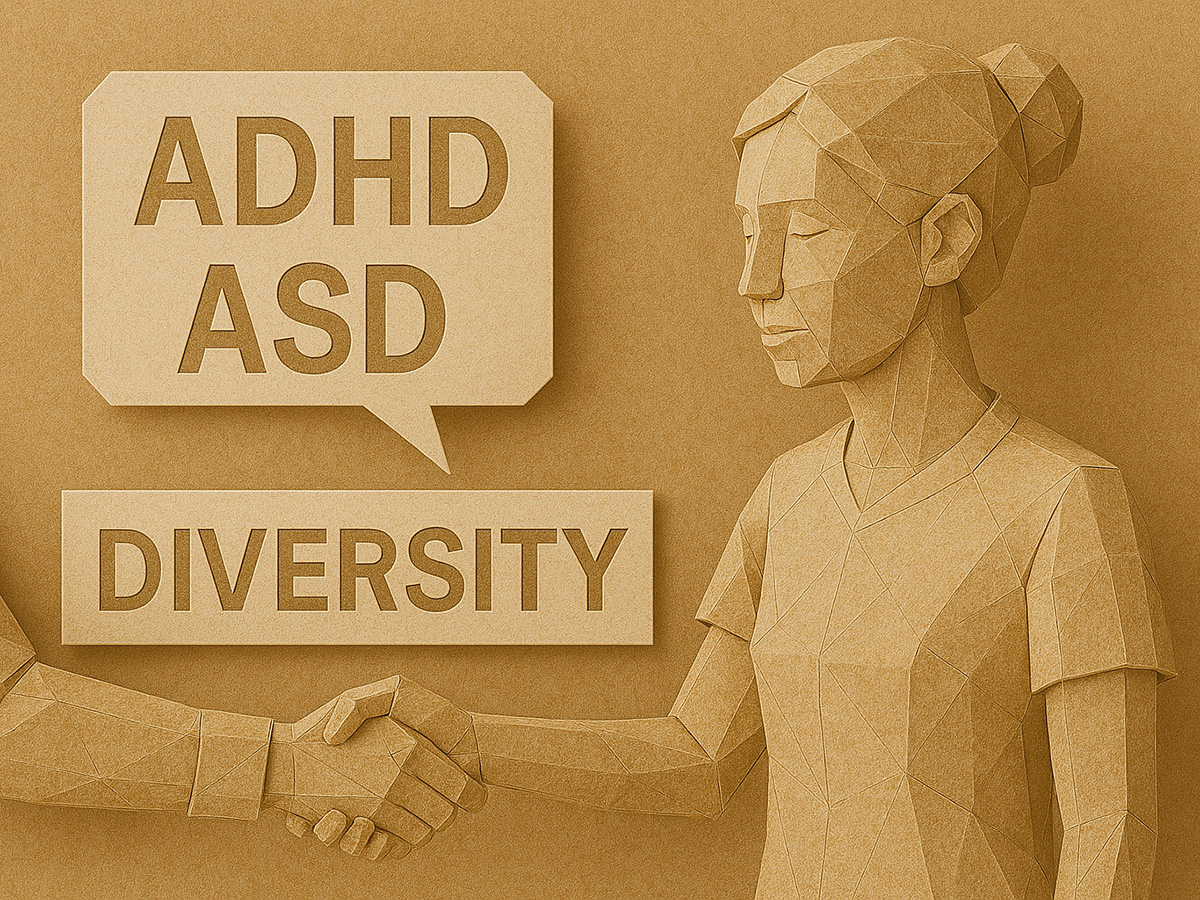 社会全体として大切にすべきは、「普通」や「正常」の基準を狭く捉えて人を排除したり、「障害」として扱ったりするのではなく、一人ひとりの多様な特徴や個性を認め合い、尊重する社会を目指すことです。「少し変わっている」「落ち着きがない」と感じる人たちを無理に病気とみなして治療するのではなく、その多様性を認め、個人個人が自分らしく生きられる社会を目指すことが必要です。
社会全体として大切にすべきは、「普通」や「正常」の基準を狭く捉えて人を排除したり、「障害」として扱ったりするのではなく、一人ひとりの多様な特徴や個性を認め合い、尊重する社会を目指すことです。「少し変わっている」「落ち着きがない」と感じる人たちを無理に病気とみなして治療するのではなく、その多様性を認め、個人個人が自分らしく生きられる社会を目指すことが必要です。
ADHDやASDを取り巻く問題は、単に診断や治療だけではなく、「人間の多様性をどう捉えるか」という私たちの価値観にも深く関係しています。
今後、このテーマに関する議論は、心理学や医療の世界を超えて、私たち一人ひとりが考えるべき重要な課題となるでしょう。
(出典:Research Gate)(画像:たーとるうぃず)
人はそれぞれ違って、多様である。それが「普通」。
そんな認識を前提に、特性で判断するのではなく、困っていて支援が永続的に必要かどうかで、「障害」とするかどうかが適切だと私は思います。
(チャーリー)



























