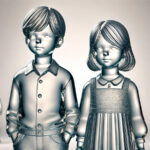- 自己申告と専門家による診断の違いは何ですか?
- どのようにしてより正確な支援を受けることができますか?
- オンライン調査の結果はどのように解釈すべきですか?
近年、自閉スペクトラム症(ASD)についての研究がオンラインで盛んに行われています。
オンライン調査は多くの人々から短時間で情報を収集できる利点がありますが、一方で自己申告だけに依存するため、診断の正確さや現実世界との関連性について疑問が指摘されています。
今回、新たな研究で、専門家が診断したASDの成人と、自らASD傾向が強いとオンラインで回答した成人との間に、意外な違いが明らかになりました。
この研究は、米ニューヨークのマウントサイナイ医科大学のサラ・バンカー博士らが中心となり実施されました。
研究者たちは、専門家による診断を受けた56人のASD成人グループと、オンライン調査プラットフォーム「プロリフィック」で自己申告したASD傾向の高い56人、さらにASD傾向が低い56人を比較しました。

まず、参加者が自分自身で評価した自閉的な特性のレベル(例えば社会的コミュニケーションの困難さや行動のこだわり)について調べました。
その結果、オンラインでASD傾向が高いと申告したグループの人々は、専門家が診断したASDグループの人々と同じ程度に、自閉症の特性が強いと自己評価していました。
しかし、社会的不安や回避性人格障害(人との接触を避ける傾向)については、オンラインでASD傾向が高いとしたグループの方が、専門家が診断したグループよりも大幅に高いことが分かりました。
これは、オンラインでの自己申告は、自閉症というよりも、社会的な不安感や自己評価の低さを反映している可能性を示しています。
さらに、実際の社会的な状況での行動を調べるために、参加者は二種類のゲームに参加しました。
一つ目のゲームでは、相手から提案されるお金の分け方を受け入れるか拒否するかを選び、自分の決定によって次回の提案内容がどのように変わるかを見て、自分が相手の行動をどれだけコントロールできるかを測りました。
二つ目のゲームでは、仮想の街に引っ越してきたという設定で、仮想のキャラクターと交流をしながら、仕事や住居を探すというシナリオで進行します。
このゲームでは、参加者が仮想キャラクターとどう交流するかを選択することで、社会的関係の築き方を評価しました。
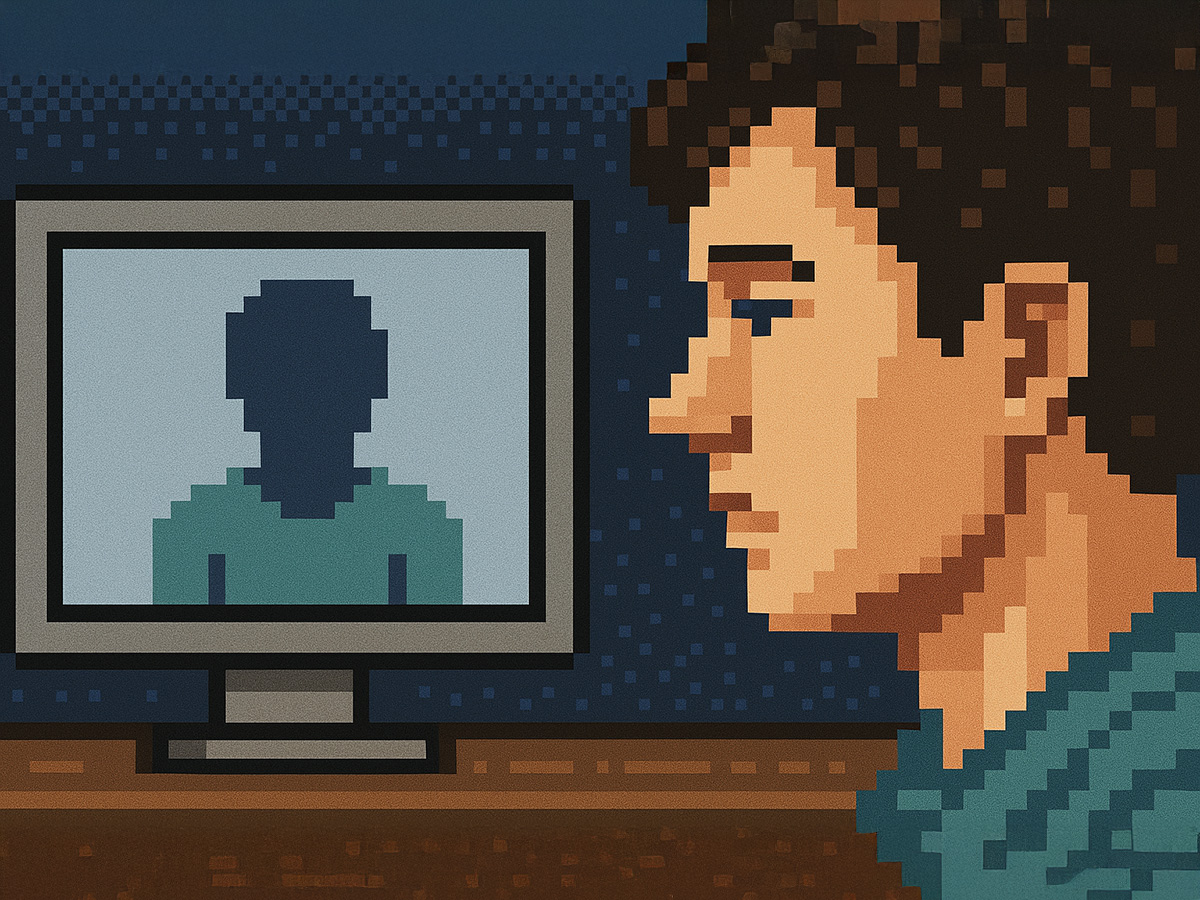
その結果、専門家が診断したASDグループは、オンラインで自閉傾向が高いと申告したグループよりも、社会的なコントロールを効果的に利用できず、また仮想キャラクターに対しても親密さを示す行動が少ないことが明らかになりました。
オンラインで傾向が高いとしたグループは、実際の社会行動においては、自閉傾向が低いグループと非常に似ていました。
この研究の最も重要な指摘は、自己申告による調査結果が、臨床的に診断された自閉症の特徴を必ずしも正確に反映していないということです。
専門家による診断と自己申告との間には大きなズレがあり、オンライン調査だけでは自閉症の特性や支援の必要性を正確に把握できない可能性があると警告しています。
研究者たちは、自己申告調査が無意味だと主張しているわけではありません。
むしろ、自己申告は個人がどのように感じているかや、内面の問題を把握する上で重要な手がかりを提供します。
しかし、臨床的な判断や第三者の評価と組み合わせて用いることで、より適切な支援や介入方法を見つけられると強調しています。
今後はオンライン調査と臨床診断を組み合わせることで、より正確で役立つ研究結果が得られることが期待されています。
この研究は、自閉スペクトラム症についての理解を深めると同時に、オンライン調査の使い方について重要な視点を与えるものとなりました。
(出典:Nature Mental Health)(画像:たーとるうぃず)
自己申告と正式な「診断」では、違うことは多いでしょう。
ぱっと見てわからない、内面にも関わることなので、たしかにどちらも重要だと思います。
本当に支援が必要な方に、適切な支援がなされるために。
(チャーリー)