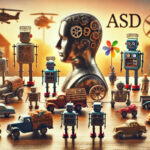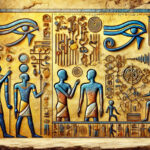- 自閉症の子どもたちが学校で十分に学ぶために、教育者はどのような理解や行動が求められますか?
- 教師の自己構築が自閉症に対する偏見や理解に与える影響は具体的にどういったものですか?
- 自閉症に関する教育プログラムをどのように改善すれば、教師の文化的背景を考慮することができるでしょうか?
自閉症(自閉スペクトラム症:ASD)の子どもが一般の学校で学ぶ機会が世界的に増えています。
しかし、このような子どもたちが学校で安心して生活し、十分に学習するためには、教師の理解が非常に重要です。
最近の研究では、教師がどれくらい自閉症について正しく理解しているか(自閉症への意識)と、自閉症の子どもに対する偏見や差別(スティグマ)の関係について、新しい視点から注目されています。
その視点とは、教師自身が自分をどのように捉えているかという「自己構築」という考え方です。
自己構築とは、自分を「独立した個人」として見るか、それとも「他人や社会との関係性の中にいる存在」として見るかということです。
たとえば、「私は創造的です」というように、自分個人の特徴で自分を表現する人は「独立的な自己構築」が強く、一方で、「私は母親です」など自分の社会的役割や他者とのつながりで自分を説明する人は「関係的な自己構築」が強いとされています。
この「自己構築」は、その人が属する文化に大きく影響されます。
アメリカやヨーロッパなどの西洋文化圏は個人主義的な社会であり、「独立的な自己構築」が主流です。
一方で、日本や中国、韓国などの東洋文化圏は集団主義的であり、「関係的な自己構築」が一般的です。

トルコのレジェップ・タイイップ・エルドアン大学で行われた研究では、教師を目指す学生や一般教育の教師1,031人を対象に、自己構築の違いが、自閉症への理解やスティグマにどのように影響するかを調査しました。
その結果、教師の自閉症に対する理解度が、自己構築の違いによって、スティグマに与える影響が変化することが明らかになりました。
具体的には、「独立的な自己構築」を持つ教師は、自閉症に対する理解が進むほど、自閉症の子どもに対する偏見や差別の傾向が減少しました。
一方で、「関係的な自己構築」を持つ教師は、必ずしもそうではありませんでした。
これは、集団主義的な文化の中では、自閉症の子どもが他者とうまく馴染めないことが、周囲との調和を乱すと捉えられやすく、その結果、偏見やスティグマが生まれる可能性があるためです。

この研究から、自閉症に関する教育や啓発活動を行う際には、教師の文化的背景や自己構築の特徴を考慮することが重要だということがわかりました。
つまり、同じ自閉症の教育プログラムを行っても、教師が持つ自己構築のタイプによってその効果が大きく変わる可能性があるのです。
研究の中では、とくに教師を目指す若い学生たちの自己構築が、文化的な一般的傾向とは異なり、個人主義的(独立的)な傾向を示すことも分かりました。
これは、教師になるための教育そのものが、教師の自己構築に影響を与え、文化的な背景とは異なる個人主義的な考え方を育む可能性を示唆しています。
さらに、研究では、参加者の多くが自閉症についてある程度の知識を持っている一方で、十分な深い理解を持っているとは言えないことも明らかになりました。
たとえば、自閉症の人が他人と関わりを持つことにあまり関心を示さないことが、特定の文化背景を持つ教師には「他者との関係を築こうとしない」と誤解されるリスクがあります。
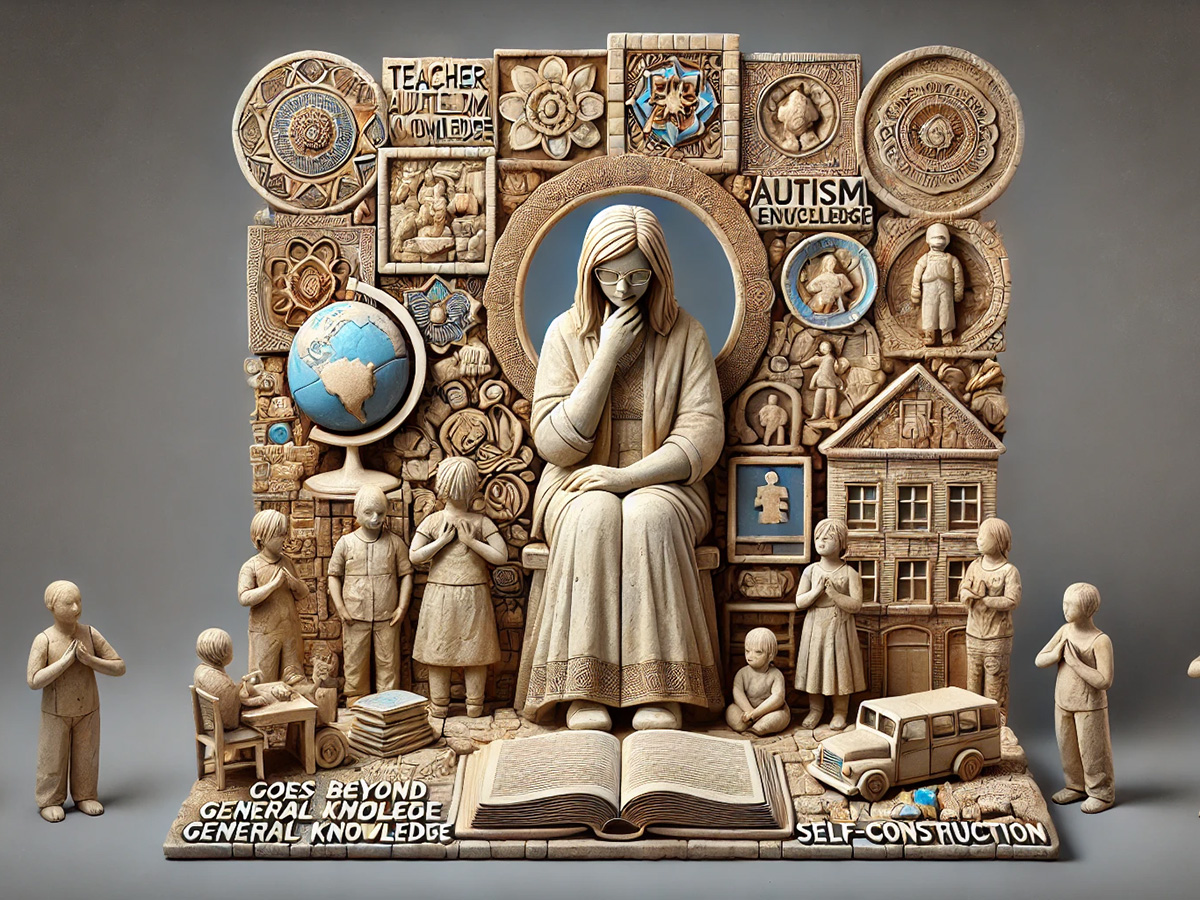
これらの結果を踏まえて、研究チームは、教師教育において自閉症に対する一般的な知識を教えるだけでなく、教師自身の文化的背景や自己構築にも目を向けることが必要だと指摘しています。
とくに、集団主義的な文化圏では、教師が自閉症に対して無意識に偏見を持ってしまうことを防ぐために、自分自身の文化的価値観を意識し、理解を深めるための教育プログラムが重要になるでしょう。
この研究が示すように、自閉症の子どもたちが一般の学校で幸せに学ぶためには、教師が単に障がいに関する知識を得るだけでなく、自分自身の考え方や価値観に気づき、それを柔軟に変えていくことが求められます。
これからの教育現場では、教師自身が文化や自己への理解を深めることが、自閉症への理解と偏見のない教育環境を作る鍵になるでしょう。
(出典:Research Gate)(画像:たーとるうぃず)
日本人であれば、「日本人は『他者と違う』ことをネガティブに捉えられがち」と自覚する人が多いように思うので、むしろ私はこういう心配はあまりないかと思ったりします。
ですが、うちの子はずっと特別支援学校だったうえに、先生には恵まれてきたので、そう思えるのかもしれません。
(チャーリー)