
- 幼児期に実行機能の発達が自閉症やADHDにどのように影響を与えるのか?
- 早期の認知的違いをどのように早期介入に活かせるのか?
- 家族に自閉症やADHDの診断歴がある子どもたちへの支援はどうあるべきか?
英オックスフォード大学をはじめ、ロンドンの主要大学や英ケンブリッジ大学、さらにはトルコの大学といった国際的な研究機関の専門家グループが手がけた最新の研究が、幼児期の「実行機能」と呼ばれる行動制御能力の発達と、その能力が自閉症やADHDの家族歴とどのように関連しているかを明らかにしました。
この研究は、2歳および3歳の幼児を対象に、反応抑制や短期記憶、注意の切り替えなど、目標達成に必要な認知機能を実験的に評価し、家族に自閉症やADHDの診断歴がある子どもたちとそうでない子どもたちとの間で、どのような違いが見られるのかを検証したものです。
研究チームは、幼児期という極めて早い段階で実行機能を評価するため、子どもたちに様々なタスクを実施させました。
たとえば、あるタスクでは「禁止されたおもちゃに触れてはいけない」というルールの下、子どもたちがその誘惑にどれだけ抵抗できるかを測定しました。
また、視線の動きを捉えることで、注意をどれだけうまく制御できるかも評価されました。
こうしたタスクを通じて、家族に自閉症やADHDの診断歴がある子どもたちは、家族歴がない子どもたちに比べ、反応抑制や注意制御の面で劣る傾向があることが明らかになりました。
とくに2歳の段階では、いわゆる「シンプルな実行機能」―具体的には、短時間の記憶保持や反応の抑制といった基本的な認知能力―において、家族歴がある子どもたちがルールを守ることに苦戦する傾向が確認されました。
あるタスクでは、禁止された対象に早く触れてしまう行動が、自閉症やADHDの家族歴を持つ子どもに多く見られたのです。
さらに、視線を用いた注意制御の課題においても、とくに自閉症の家族歴がある子どもたちのパフォーマンスが低く、注意力の制御における早期の違いが示唆されました。
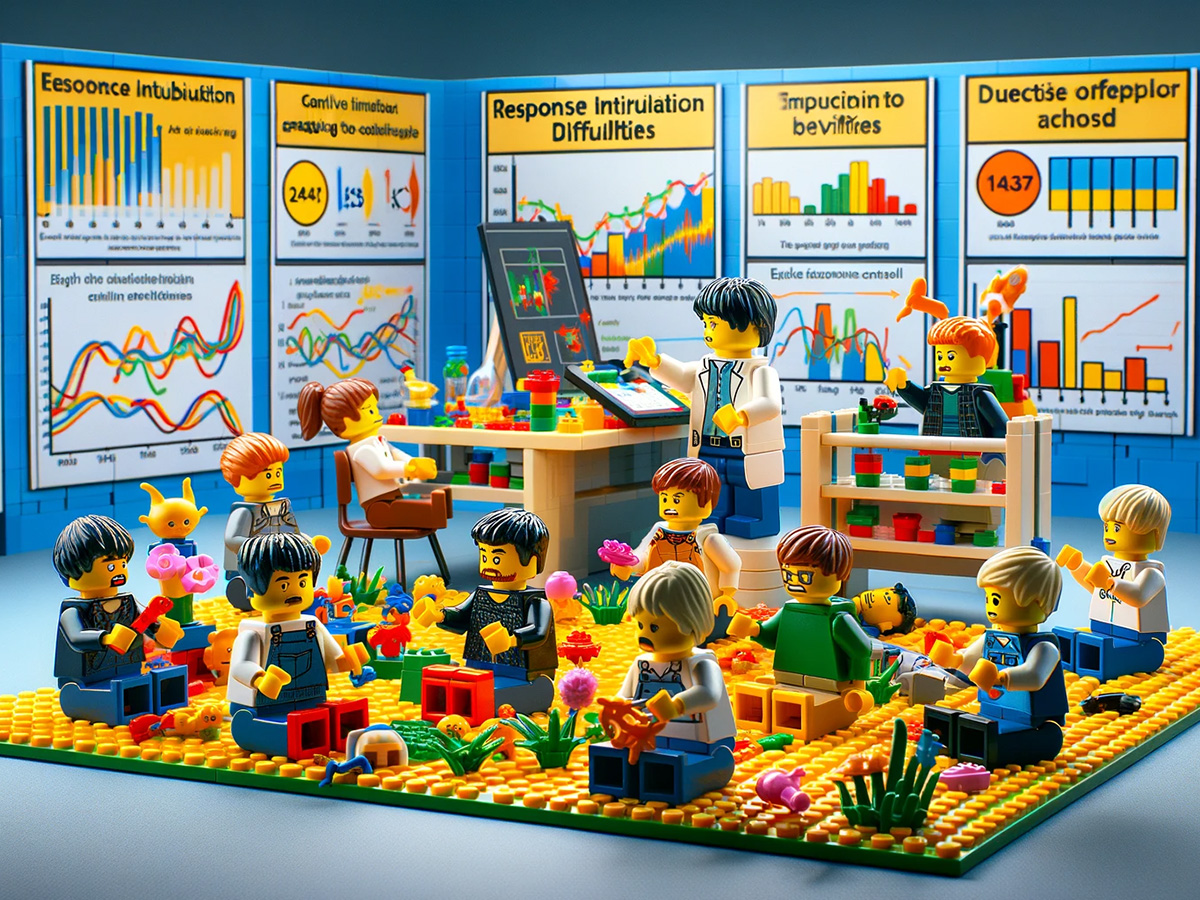
3歳に成長すると、実行機能はより高度な「コンプレックスな実行機能」へと発展していきます。
ここでは、単にルールを守るだけでなく、情報の更新やタスクの切り替えといった、複数の認知プロセスを統合する能力が求められます。
研究結果によれば、家族歴のある子どもたちはシンプルな実行機能だけでなく、複雑な実行機能においても劣るケースが見られ、とくに自閉症とADHDの両方の家族歴がある子どもでは、これらの高度な認知制御がさらに低い傾向にあることが示されました。
また、保護者からの行動評価もこの研究の重要な要素です。
2歳時点でのタスクパフォーマンスは、後の自閉症やADHDの傾向とある程度の相関関係を持っていることが確認されました。
具体的には、早い段階での反応抑制の弱さが、3歳時点での自閉症やADHD関連の行動特性と結びついており、幼児期からの認知的違いがその後の発達にどのように影響を及ぼすかを示す貴重な手がかりとなりました。

この研究の魅力は、幼い子どもたちにおける発達の初期段階で、遺伝的なリスクが実行機能の発達にどのような影響を与えているのかを、実験的に詳細に検証した点にあります。
従来、実行機能に関する研究は学齢期以降や成人期が中心でしたが、今回の研究は2歳や3歳という極めて早期の時期に焦点を当てたため、将来的な支援や早期介入の可能性についても新たな示唆を提供しています。
研究チームは、今回の成果をもとに、たとえば反応抑制や短期記憶の基本的なスキルを育成するためのプログラムを提案しています。
こうした介入が、将来的に自閉症やADHDの診断に至らなくとも、子どもたちの学習能力や社会的適応力の向上に寄与する可能性があると考えられます。
また、自閉症傾向が見られる子どもたちに対しては、情報の更新や注意の柔軟な切り替えといった高度な認知プロセスを補完するための、より専門的な支援策も検討されるべきだという議論が展開されています。
今回の研究は、オックスフォード大学実験心理学部門を中心とする研究グループが、複数の国際的な研究機関と連携して実施した大規模なプロジェクトです。

家族に自閉症やADHDの診断歴がある子どもたちは、現時点で臨床的な診断に達していなくても、すでに実行機能の一部において明確な違いが現れていることが示されました。
これにより、幼児期の認知的発達の初期段階から、将来の行動や適応に影響を与えるリスクを早期に察知し、適切な介入を行う重要性が浮き彫りになったのです。
このような研究成果は、親や教育者、そして医療従事者にとっても大きな関心を呼び、幼児期からの発達サポートのあり方について改めて考える契機となっています。
実行機能という一見単純な認知能力が、将来的な社会生活や学習、ひいては精神的健康にまで影響を及ぼす可能性があるという事実は、子どもたちの健全な成長を促すための早期介入策の構築に向けた大きな前進を意味しています。
国際的な研究ネットワークのもとで進められた今回の研究は、幼児期の発達における遺伝的要因と認知機能の関連性を具体的な数値やタスク評価を通じて明らかにした点で、今後の臨床研究や介入プログラムの設計に大きな影響を与えると期待されています。
子どもたちの未来をより明るくするための新たな支援策の開発に向け、専門家たちはこれからもさらなる追跡調査や新たな実験手法の開発に取り組むことでしょう。
(出典:Nature)(画像:たーとるうぃず)
かかえる困難が軽減することにつながる効果的な療育。
それに貢献する研究、そして実践、よろしくお願いします。
(チャーリー)



























