
- 大人になってから自閉症の診断を受けるには、どのようなステップが必要ですか?
- 自閉症を公表することのメリットとデメリットは何ですか?
- 自身の特性を理解し、受け入れてくれる環境をどのように見つけることができますか?
私は「他の子」とは違う子供でした。
何かにとても没頭すると、その話題についてひたすら語り続けたり、周りの微妙なサインに気付かなかったり、会話中にふと意識が遠のいて壁を見つめたりしていました。
子どもたちが小さい頃、なぜテレビのスイッチを入れずにテレビを「見ている」のか、不思議がられたこともありました。
私は53歳になって初めて、正式に自閉症と診断されました。
現在、アメリカでは36人に1人の子どもが自閉症と診断されるようになりましたが、これは自閉症スペクトラムの定義が見直され、自閉症がこれまで十分に診断されず、配慮も不足していたことが認識された結果です。
診断を受けてから6年間は自分のことを公にしませんでしたが、その後、自閉症の科学者たちが生物医学の分野にもたらした貢献に気付き、私自身以上に多くの困難を乗り越えている彼らの話を学ぶようになりました。
近年、ロバート・F・ケネディ・ジュニア氏の承認をめぐる政治的論争で、彼が根拠のない「ワクチンが自閉症を引き起こす」という説を広めたことで、その苦労は一層浮き彫りになっています。
また、自閉症を「個性」「障害」あるいは「病」と捉えるかについて、どう研究し、対応し、語るべきかという議論があることも知りました。
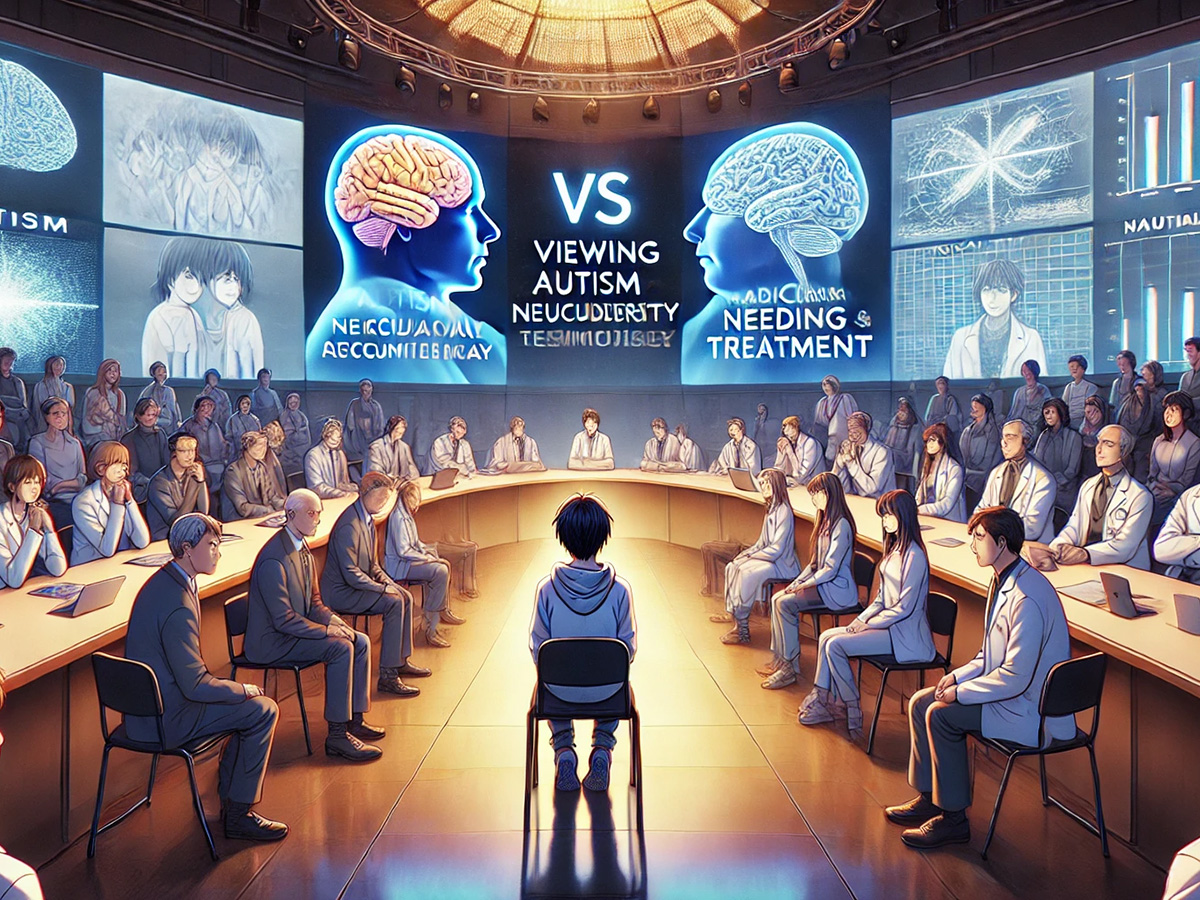
この対立が自閉症を持つ科学者たちにとって、さらなる負担となっているのです。
多くの方々が、これらの困難を乗り越えながらも重要な貢献をしており、その共通点は「適切なパートナー選び」にあると感じます。
私たちが全ての優秀な頭脳を科学に向け、支援する時代だからこそ、より良い科学の基盤を築くには、神経多様性を超えた協力という考え方を受け入れることが不可欠です。
私の診断を公表して以来、自閉症と診断された、あるいは自分が自閉症かもしれないと感じている多くの生物医学関係者から、アドバイスを求める声をいただいています。
大人になって診断を受けるにはどうすればよいのか?
診断結果を公表すべきか?
自分を受け入れてくれる指導者や研究室をどう見つけるのか?
多くの人が、社会的なコミュニケーションの難しさや、科学の現場で歓迎されにくいという悩みから診断を求めているのです。
私自身は、これらの質問に対して、より経験豊富な人たちを紹介するようにしています。
実は私も、他の多くの自閉症の科学者と同様に、59年間も自分の自閉症の特徴を隠してきました。
診断が多くの疑問に答え、かけがえのないものとなった一方で、私が診断を受けたのは360度の評価の結果であり、自ら積極的に求めたわけではありません。
つまり、私が得意なのは、非言語的なサインを見落としたり、あまりにも率直すぎて気づかない失敗について、謝る方法くらいなのです。
しかし、私がこれまでやってこられたのは、人生や仕事において自分の弱点を補ってくれるパートナーを選び抜いてきたからだと強調したいと思います。

自閉症の特徴としては、非言語的なサインを読み取るのが苦手だったり、会話の切り上げ方が分からなかったり、身振りや声の抑揚、表情を通じたコミュニケーションが難しいことなどが挙げられます。
また、「ダブル・エンパシー問題」と呼ばれる現象があり、これは私たちが他人の感情を理解する認知的共感力は低い一方で、他人の感情を自分自身が感じ取る情動的共感力は高いというものです。
このため、周囲の人々は、私たちが本当はつながりを求めているにもかかわらず、つながる気がないと誤解してしまいがちです。
こうした違いを補ってくれるパートナーや協力者は、往々にして社交的で、非言語コミュニケーションが得意な人たちです。
私自身も、配偶者や親しい友人、研究の指導者など、こうした特性を持つ人たちをずっと探してきました。
意識的にそうしていたわけではありませんが、こうしたパターンが、より多様な神経タイプを受け入れる科学の場を作る上でのヒントになるのではないかと感じています。
米ピッツバーグ大学の精神医学教授で自閉症を研究しているグレッグ・シーグルは、自身も自閉症であり、神経画像診断を用いて、自閉症の人々が感情的な出来事に対して、時に過剰に反応したり、逆に全く感情を表に出さなかったり(あるいは一見普通の反応を示したり)する理由を解明しようとしています。
シーグルは、診断を受ける前の18年間、研究グループや同僚との衝突に苦しんできました。
私がシーグルに、自閉症の研究者を科学の現場によりよく受け入れるためのアイデアを尋ねたところ、こう語ってくれました。
「自分らしくいられる研究室の環境を意識的に作ることが重要です。
しかし、これは言うは易く行うは難しというのが現実です。常に自分を隠し続けていては、ただ隠すことにエネルギーを費やすだけで、研究が進まなくなります。
一方で、誰もが安心して働ける環境を作らなければ、研究室から『叫びながら逃げ出す』人が出てしまいます。
だからこそ、意識的に居心地の良い環境を作ることは、今のところ科学でありながら芸術とも言える作業ですが、時間をかける価値は十分にあると思います」
また、若い研究者が自分の自閉症を公表することについても多く考えているそうです。

「自分が自閉症であることを明かすには、メリットもあればデメリットもあります。
しかし、重要なのは、単に自分が自閉症であると公表するのではなく、どう一緒に働くのが最適かという情報を伝えることです」
彼自身は、メンターや協力者に対して、自分との接し方の「ユーザーガイド」を渡すことで、円滑なコミュニケーションを促しています。
米UCLAの非自閉症研究者エミリー・ホテスは、自閉症で支援が必要な妹を持つ立場から、より多くの人が自分の状態をオープンにすることが理想だと考えています。
「偏見を感じることは、精神面に大きな負担を与えます。
偏見を予期するだけでも、体に同じようなストレス反応が生じ、精神的・肉体的健康に悪影響を及ぼすことが科学的に明らかになっています」
だからこそ、自己開示はとてもハードルが高いのです。
しかし、その一方で、隠し続けることも決して良い選択ではありません。
「調査によれば、自閉症の人の75%が何らかの形で自分を隠そうとしているとされています。
とくに自閉症の女性は、隠すことで大きな疲労を感じ、それが深刻な精神的・身体的健康問題につながっているのです」
米ノースカロライナ大学の非自閉症の産婦人科教授であり、自閉症の息子を持つローレン・シフ教授も、最近『ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン』に、自閉症患者への配慮の方法についての記事を執筆しました。
彼女もシーグルやホテスと同様に、自己開示について重要な問題だと認識しています。
「患者がクリニックや医療環境に入る時と同じように、職場や科学・医療の現場でも、周囲の人たちが自分のニーズを理解し、柔軟に対応してくれるべきだという期待がある。
しかし、もしそうならなかった場合、その壁を乗り越えるのは一層難しく感じられる」
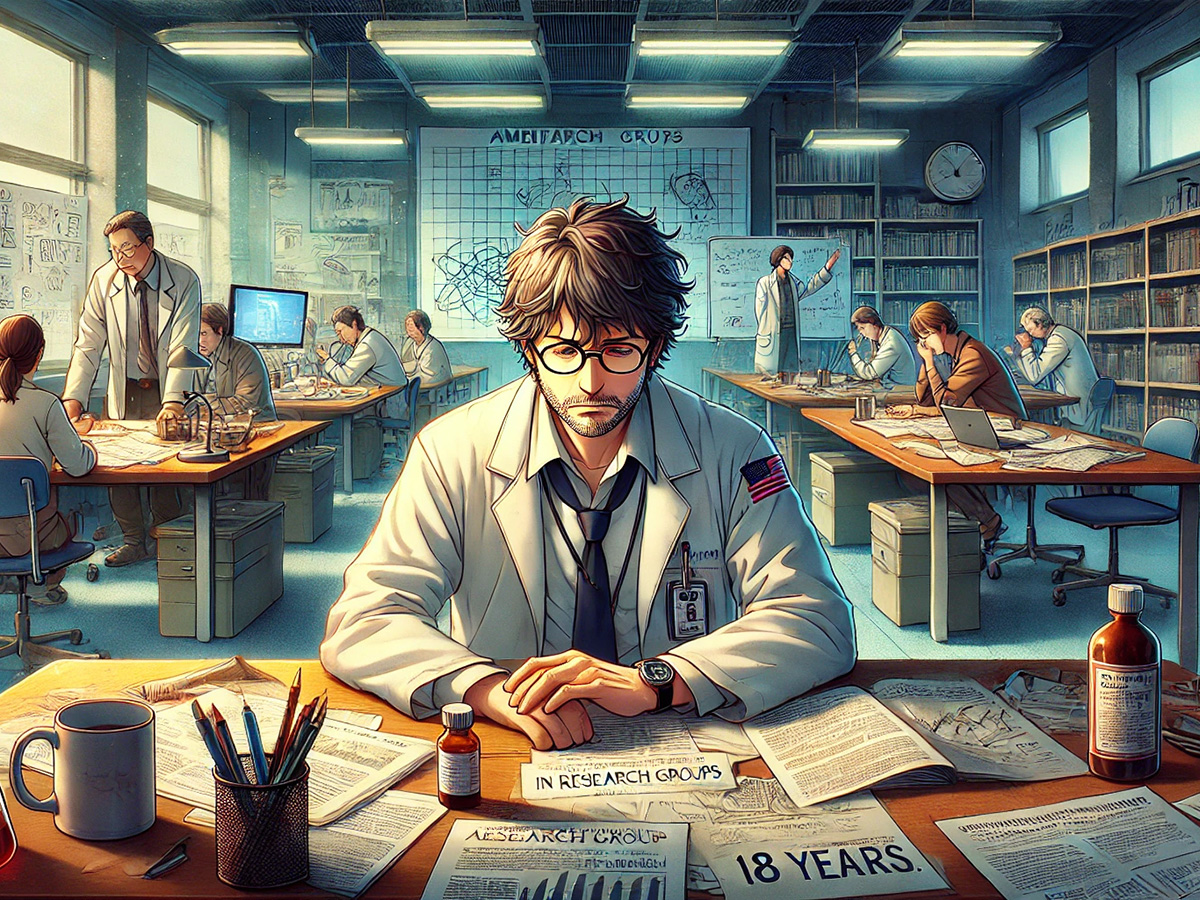
生物医学の現場で自閉症の研究者として働くということは、同時に自閉症そのものを研究する環境の中で働くことを意味します。
自閉症は、神経学的な違いとして社会的な配慮で対応すべきだという見解と、医学的な「障害」として研究し、治療すべきだという見解との間で、コミュニティ内で意見が対立しているのは周知の事実です。
自閉症の研究者は、常に細やかなケアを必要としない分、社会モデルに賛同しやすいですが、隣接する研究室や自分自身の研究室では、遺伝子研究や介入の可能性についての優れた研究が行われているのも事実です。
このような環境下で働く自閉症の研究者たちは、自分たちのアイデンティティを消し去ろうとする同僚がいるのではないかという思いにも向き合わなければなりません。
シーグルにこの点について尋ねたところ、こう語りました。
「私たちは、異なる人々と一緒に働くなら、まずは周囲の人々を理解する努力をするべきです。
たとえ医学モデルに賛同しなくても、医学的な理解と社会的な理解とのつながりに気づき、矛盾していないことを認識する努力は必要だと思います」
また、シーグルは、自閉症でない研究者が自閉症の人々に対して感情的・知的な労力を無理に求めないよう配慮すべきだとも考えています。
「自分が自閉症だからといって、すべての自閉症に関する分野で専門家である必要はありません。
私たちが雇われた仕事を、他の同僚と同じレベルの理解と配慮のもとでこなすことが許されるべきだと思います」
実際、ほとんどの非自閉症の研究者は、自分たちの自閉症の同僚を理解したいと願っています。
シフ教授は、自閉症の患者にどう配慮するかを話すと、多くの「もっと良くするにはどうすれば?」という質問を受けると語っていました。
同様に、シーグルも、映画『レインマン』のような固定観念から脱却することの重要性を強調します。
「あなたは自閉症に見えない」と言われたとき、彼はこう返します。
「では、あなたは自閉症の人はどんな風に見えると思っていますか?
その根拠はどこにあるのですか?」
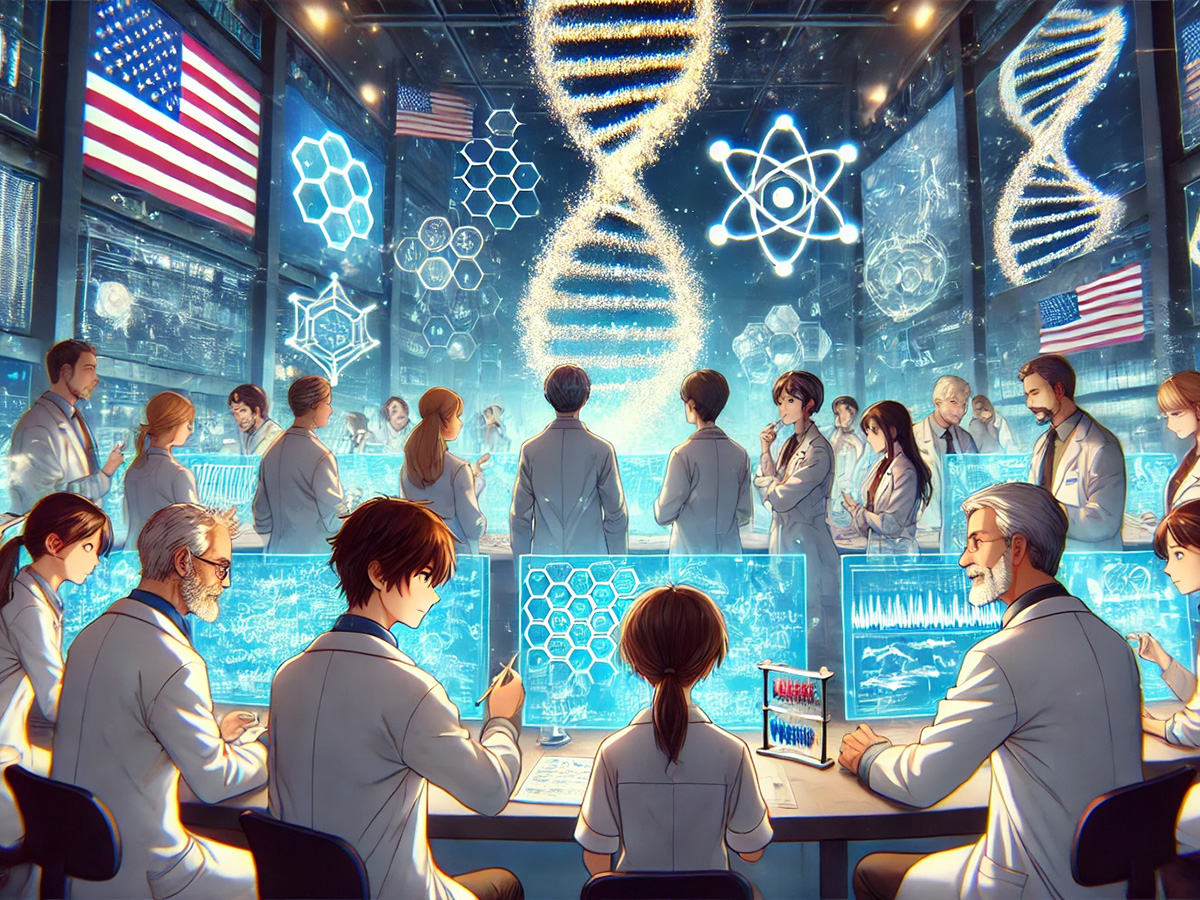
私が関わってきた多くの人が口を揃えて言うのは、自閉症の研究者が成功する鍵は「協力」に尽きるということです。
自閉症の研究者は、自分たちの特性を補完してくれる自閉症でない研究者と協力する必要があります。
シーグルによれば、「それは、私たちにとっては社会的スキルの問題です。そこで、とくにその面に長けたコーディネーターを雇うのが一つの解決策です」とのことです。
逆に、自閉症でない研究者は、広範な自閉症スペクトラムやこれまでの自閉症に関する考え方の変化を理解するために、自閉症の研究者と協力する必要があります。
そして、自閉症の研究者同士も、どの神経多様性モデルが最良かという対立ではなく、理解と啓発のために互いに協力すべきなのです。
理想を言えば、こうした協力体制こそが、誤った情報に惑わされることなく、科学的根拠に基づいた神経多様性の理解を推進するために必要だと考えています。
しかし、ホテスも「自閉症の分野がもっとまとまり、神経多様性の理念と科学に沿った統一されたメッセージを発信できるようになるのは、すぐに実現するとは思えない」と語っています。
たしかに、これは非常に大きな課題であり、克服が難しいように思えるかもしれません。
しかし、シーグルに、自閉症に対する自分の考えに反論されることにどう対処するか尋ねたところ、彼はこう答えました。
「私たちは皆、他の人とは違った視点で自閉症やその他の事柄について考える権利があります。
それぞれの人が異なるレベルのケアを必要とし、様々な視点を持っている。
だからこそ、私はどんな意見も正当で価値があるものだと認めるよう努めています」
私も同じ考えです。
もし、私たちがこうした多様な視点をより頻繁に認め合えるようになれば、すべての人を包み込み、神経多様性について実用的な知識を生み出す、より強固な科学の基盤を築くことができるでしょう。
ホールデン・ソープ
『Science』の編集長、米ジョージ・ワシントン大学 化学・医学教授
(出典:米STAT)(画像:たーとるうぃず)
人が違うのは当たり前で、お互いに違うことを認め、違うことを尊重することで、協力するメリットが得られるのだと私も思います。
(チャーリー)



























