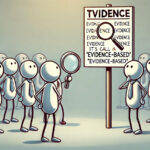- 音楽療法は自閉症の子どもにどのような具体的な効果をもたらすのか?
- どのような条件や方法が音楽療法の効果を最大化するのか?
- 音楽療法を受けた子どもたちの社会的スキルや感情表現はどの程度改善されるのか?
自閉症スペクトラム障害(ASD)とは、社会的なコミュニケーションや感情の共有が苦手で、限られた興味や反復行動を示す発達障害です。
近年、世界的にこの障害を持つ子どもの数が増え続けており、注目が高まっています。
そのようななか、音楽を使った治療法「音楽療法(ミュージックセラピー)」が、自閉症を抱える子どもたちの社会的な能力や感情表現を改善する可能性があるとして注目されています。
今回、サウジアラビアの複数の大学からなる研究グループが、2009年から2024年までに実施された9つの質の高い研究(ランダム化比較試験)を分析しました。
対象は2歳から12歳の自閉症の子ども合計1,327名。週に1~3回の音楽療法を2週間から8ヶ月間行った結果を検討しました。
分析対象となった9つの研究は、それぞれ異なる年齢層・療法内容・測定方法を用いながらも、音楽療法のもたらす効果を検証していました。
以下は主な研究の概要とその結果です。
・ウィリアムズら(2024年)の研究では、2〜5歳の子ども27名を対象に、週2回・18週間にわたって「音楽アシストプログラム(MAP)」を実施。他の介入法(SCIP-I)と比べて、社会的反応性や語彙の面でより大きな改善が見られました。
・シャルダら(2018年)の研究では、6〜12歳の子ども51名を対象に、週1回の音楽介入を8〜12週間行いました。社会的コミュニケーションスコアが平均で4.84点改善し、脳の前頭葉と側頭葉を結ぶネットワークの機能的接続が高まったことが脳画像検査で確認されました。

・ジェレツェガーら(2011年)は、4〜7歳の子ども300名を対象に、即興的音楽療法(IMT)を週1〜3回、5ヶ月間実施。社会的関与と反応性の向上が見られ、特に頻度の高いセッションを受けた子どもに顕著な効果がありました。
・リムとドレイパー(2011年)は、3〜5歳の子ども22名に対してABA(応用行動分析)と音楽療法を組み合わせ、言語スキルの発達を評価しました。結果、模倣や単語使用(エコーイック反応など)が有意に向上しました。
・キムら(2009年)の研究では、即興音楽療法を受けた10人の子どもたちにおいて、感情的な同調、喜び、自発的な関わりの増加が記録され、音楽療法が情動・動機づけに好影響を与えることが確認されました。
・グリーンら(2010年)は、2〜4歳児152名に対して、保護者主導型の音楽療法的コミュニケーション介入(PACT)を半年間実施し、ADOSスコア(社会的相互作用の指標)が中程度の効果量で改善されました。
一方で、以下の研究では、明確な主効果は確認されなかったものの、いくつかの副次的指標で改善が見られました:
・ビエレニニクら(2017年)とクロフォードら(2017年)の研究では、IMTと通常ケアを比較し、主要なADОSスコアには有意差が出なかったものの、社会的動機づけや反応性といったサブスケールでは小規模ながら有意な改善が見られました。
・ラベイロンら(2020年)は、音楽療法と音楽視聴を比較し、8ヶ月間にわたり25回のセッションを行いました。音楽療法グループでは臨床的な改善が顕著に見られ、行動問題の改善度を示すABCスコアやCGIスコアに大きな効果(Cohen’s d = 0.80)が示されました。

このように、複数の研究において、音楽療法が社会的コミュニケーション、言語能力、感情的応答性、行動の安定性など、多様な側面に効果をもたらすことが示唆されています。
ただし、介入内容やセッション頻度、子どもの年齢、発達段階によって効果の程度には違いがあり、効果が限定的だった研究もあります。
また、音楽療法が社会的コミュニケーションに関わる脳の部位(前頭葉と側頭葉)のつながりを活性化させるという脳科学的な研究結果も得られました。
このように音楽を通じて社会的な能力の向上が、神経学的なレベルで実際に起こっていることが確認されたのです。
音楽という身近で楽しみやすい手段が、自閉症の子どもたちが抱えるコミュニケーションや感情表現の難しさを克服する一助となる可能性があることは、大きな希望と言えるでしょう。
今後、さらに研究が進むことで、より効果的な音楽療法の形が明らかになることが期待されます。
(出典:The Cureus Journal of Medical Science)(画像:たーとるうぃず)
音楽をつかった療育が悪いわけがありません。
うちの子も小さな頃から音楽は大好きです。
ますます、効果的になるように研究、検証が進むことを期待しています。
(チャーリー)