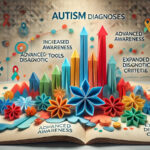- 障害を持つ学生が研究に参加することでどのような新しい視点がもたらされるのか?
- 研究室での障壁を減らすために、どのような具体的な取り組みが効果的なのか?
- 障害を持つ学生を研究者として受け入れるために、どのように意識を変えていくべきなのか?
学者や教育者は、障害を持つ学生に影響を与える研究を進めています。
しかし、障害を持つ学生が実際にその研究にどれほど影響を与えているでしょうか?
答えは「十分とは言えない」というのが現状です。
データによると、障害を持つ学生は大学での研究体験において十分に代表されておらず、知識を生み出す担い手としても、研究の機会としても見落とされがちです。
技術、医学、教育といった分野で、障害を持つ人々にとって意義のある研究を行うためには、彼らの意見を単なる研究参加者としてではなく、共同研究者として研究の設計段階から取り入れることがとくに重要です。
障害を持つ学生を早期かつ頻繁に研究に関わらせることで、問題の解決や疑問への回答に新しく独特な視点がもたらされます。
また、研究の結果や学者たちの推奨からも、職場において障害を持つ人々が増えると、誰もがイノベーションや創造的な問題解決を促進できることが示されています。

米国では、障害を持つ若者が高等教育に進むケースが増えており、全大学生のおよそ20%が自身の障害を大学に報告しています。
学生が研究に参加することは、大学生活の充実や学びの意義を実感させ、継続的な高等教育への取り組みを促進する大切な要因です。
しかし、制度的・社会的な多くの障壁が、障害を持つ学生の研究参加や、その後の科学分野でのキャリア形成を妨げています。
私たちは、ミズーリ大学コロンビア校のマスマティクス・ポテンシャル・ラボ、ポートランド州立大学のキャリア・アナリスツ・ラボ、セントルイス大学のクローム(Collaborative Haptics, Robotics and Mechatronics)ラボという3つの大学キャンパスにまたがるインクルーシブな研究室で活動する学者や学生として、障害を持つ学生が研究室に参加する際の障壁を取り除くための、意図的かつ効果的な実践と提言を紹介します。

障害を持つ学生を研究室に参加させるための具体的なアドバイスは次です。
- 積極的な招待
キャンパスの障害支援センターなどと協力して、研究室の空きポジションを積極的に周知し、障害を持つ学生に参加を呼びかけるよう努めましょう。 - 面接方法の工夫
面接での困難は、その学生の働く意欲や学業の能力を必ずしも反映していません。
たとえば、面接の質問を事前に提供したり、オンライン面接中にチャットで質問を表示することで不安を軽減する、過去の実績やポートフォリオを確認する、試しに研究室で活動してもらう、教員の推薦状を参考にする、またはシナリオに基づいた課題を実施してパフォーマンスを観察するなど、通常の面接以外の方法を取り入れるとよいでしょう。 - アクセシビリティの確保と必要な配慮
対面参加やZoomでの参加、複数の照明や座席オプション、個々にカスタマイズできる作業スペース、読みやすいテキストフォーマットなど、利用可能なアクセシビリティオプションを把握し、必要に応じて提供してください。
詳しい提案については、バーバラ・サンドランドらの文献を参考にしてください。研究室内に支援的で協力的な文化を作るため、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れることが重要です。 - 学生一人ひとりとの信頼関係を築く
どのような言葉遣い(パーソン・ファーストかアイデンティティ・ファーストか)を好むか尋ね、情報開示や自己主張を促す環境を整え、彼らが最も能力を発揮できる方法について意見を聞く時間を設けましょう。 - インクルージョンや障害に関する知識を深める
障害を持つ学生を参加させる前後を通じて、たとえば、代替のコミュニケーション手段や座席オプションを整えるなど、全ての学生が平等に参加し自己表現できる環境を作りましょう。
障害を持つ学生が、研究に平等な共同研究者として歓迎され、彼らのペースで業務に取り組めるよう配慮してください。 - 研究室の構造や活動、環境
ユニバーサルデザインの視点を取り入れ、障害を持つ学生も他の学生と同等に関与できるよう努めましょう。
共感的な視点で、障害に対するプライドを持つ考え方を採用し、全員の研究貢献を公平性の観点から認識してください。
たとえば、全ての研究室メンバーが同じようにテキスト読み上げ支援技術を必要とするわけではありませんが、視覚障害や光過敏症を持つ学生には、そのような支援がなければ平等に参加できない場合があります。
支援技術は、長時間のスクリーン作業などにおいて、障害の有無に関係なく公平な環境を整えるためのものであり、必要な人にのみ提供されればよいのです。
これは、単に「平等」であるかではなく、「公平」に参加できるようにするための必要な配慮です。

障害を持つ学生にとって、研究室への参加は、自分と似たような先輩やロールモデルがいないため、選択肢として浮かびにくい場合があります。
学部生であり本記事の共著者でもあるテイラーは、次のように説明しています。
「STEM分野の女性として、STEMの多くの研究室はとても単調で、昨日は大学の授業での研究室活動中に、本当に限界を感じました。
自分に合った配慮があまりなく、やる気を引き出す要素も十分ではなかったのです」
テイラーの経験は、彼女が興味を持つ分野における教育機会が不足しており、非常に圧倒されるものでした。
また、別の共著者であり学部生のシモンは、STEM分野に興味はあったものの、これまで研究経験がなかったため、経験を求める機会を見つけるのが難しかったと語っています。
「経験がないと、何か価値のあることを始めるのは本当に難しいです。
まるで、研究室で床掃除だけをするようなもので、それは私が望むものではありません」
さらに、研究に関する誤解も参加の障壁となりました。
研究室参加者のエマはこう言います。
「研究について聞くのは、プレッシャーが非常に高く、締め切りも多く、やることが山積みという話ばかりで、始めるのがとても怖かった」
エマは、学業面で苦労している自分にとって、そうした話は大きな障壁でした。
キャンパス内で研究室の情報を得るきっかけとして共通していたのは、「招待」でした。
各学生は、信頼できる友人や教員、あるいはキャンパスの障害支援センターからの募集メールを通じて、この機会を知ったと回答しています。
研究室での包括的な参加の実績がなければ、障害を持つ学生自身が自発的に研究の機会があると気づくのは難しいのです。

学生たちは、ミズーリ大学のマスマティクス・ポテンシャル・ラボが障害を持つ学生を積極的に募集していたことが、自分たちが研究室に参加するきっかけになったと口を揃えて言っています。
研究室のアドバイザーであり本記事の共著者でもあるジェシカ・ロドリゲスが「障害分野から採用したい」と積極的に学生を探していたことが、エマに「私の状況にも配慮してくれるチームであるという印象を与えました」。
テイラーもこう言います。
「それが決定的な理由でした。
自分が何か独自の視点を提供できると感じたからです」
ケイトもこうです。
「高等教育の現場で障害を持つ人が取り上げられることは少ないので、私はその研究室に興味を持ち、連絡を取りました」
これらの学生の意見は、キャンパス内の障害支援オフィス、社会活動、研究スペース、ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョンに関するイベントなど、さまざまな場所や形式で幅広く募集活動を行うことの重要性を示しています。
メール、ポスター、アウトリーチ活動、1年生向けの講義、アドバイザーへの情報提供など、研究に参加した障害を持つ学生たちが提案する創意工夫は多岐にわたります。
募集資料では、研究室が障害を持つ「研究対象者」を求めているのではなく、積極的に関与する「研究者」として障害を持つ学生を募集していることを明確に伝えましょう。
なお、学生たちは、誰も自分の障害を理由に参加を求められることを望んでいないとし、障害を持つ学生を募集し配慮ある環境を整える真の目的は、多様な視点や実体験を活かして強固で創造的な研究チームを作ることだと強調しています。
(出典:米Inside Higher Ed)(画像:たーとるうぃず)
「障害を持つ学生を募集し配慮ある環境を整える真の目的は、多様な視点や実体験を活かして強固で創造的な研究チームを作ること」
大学の研究室に留まる話ではありません。
社会全体にとってもそうでしょう。
(チャーリー)